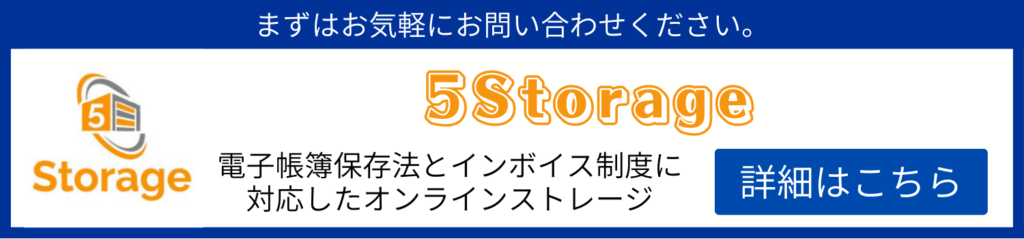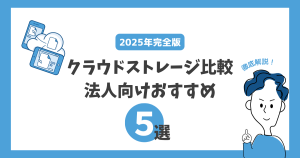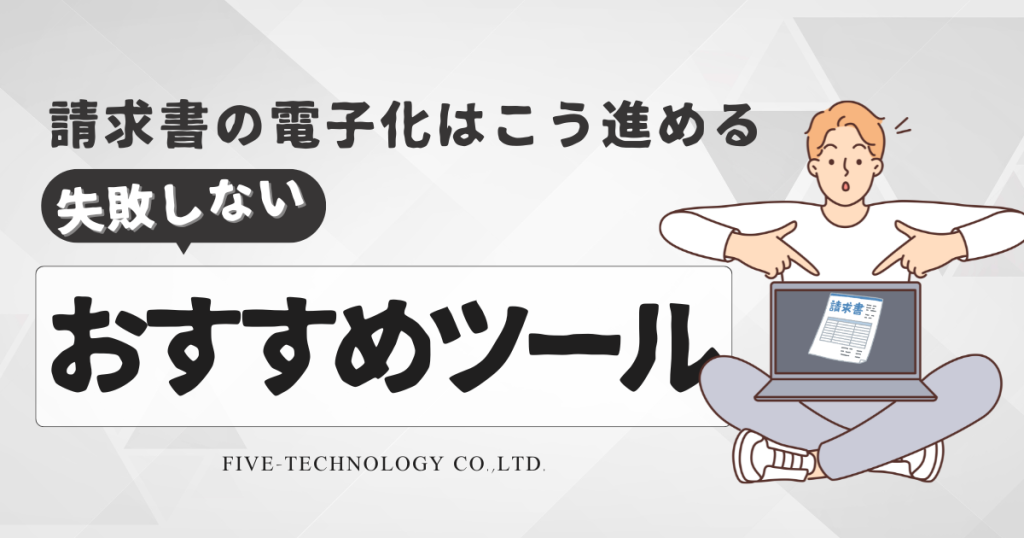
近年、請求書の電子化が中小企業から大企業まで急速に進んでいます。インボイス制度や電子帳簿保存法など、法制度の変化により「紙の請求書では対応しきれない」時代に突入したと言っても過言ではありません。
本記事では、請求書を電子化する方法・導入ステップ・おすすめのクラウドツールまで、わかりやすく解説します。これから電子化を検討する企業の担当者はぜひ参考にしてください。
請求書の電子化とは?いま注目されている理由
- インボイス制度・電子帳簿保存法への対応
2023年からスタートしたインボイス制度と、2024年以降の電子帳簿保存法対応により、デジタルでの取引情報の保存が義務化・推奨されています。
- 紙の請求書による手間とコストの限界
印刷、封入、郵送、保管、ファイリングなど、紙の請求書には多くの手作業とコストがかかります。月に数百枚以上の発行がある企業では特に負担となります。
- DX推進でバックオフィス業務の効率化が急務に
人手不足の中でバックオフィス業務を効率化するため、請求書の電子化は最初の一歩として非常に効果的です。
請求書を電子化するメリットとは
- 発行・送付作業の自動化
請求書の作成からメール送付、PDF化までを一括で自動処理でき、作業時間が大幅に短縮されます。
- 紙・印刷・郵送コストの削減
毎月の印刷代や郵送代をカットでき、年間数十万円のコスト削減になるケースも。
- 管理・検索・保管の効率化
クラウド上で保管・検索が可能となり、書類を探す時間もゼロに近づきます。
- 誤送信・紛失のリスク軽減
電子送信により封筒の入れ間違いや紛失リスクが減少します。履歴管理も容易です。
- 法令対応の強化と監査対応の簡素化
電子帳簿保存法に準拠した保存ができれば、税務調査時の対応もスムーズになります。
請求書電子化の方法|導入ステップ5つ
- 現在の請求業務フローを可視化する
誰が・いつ・何をしているかを洗い出し、非効率な部分や属人化している業務を明確化しましょう。
- 電子化に必要な社内ルールを整備
電子送付のタイミング、承認フロー、保管ルールなど、最低限の社内ルールを決めておくことが重要です。
- 適した電子請求システムを選定
自社の業種・請求件数・担当者のITリテラシーに応じて、導入しやすく、拡張性のあるツールを選びましょう。
- スモールスタートでテスト導入
まずは1部署・1取引先などで導入し、運用面や取引先の反応を確認したうえで全社展開へ。
- 全社展開と運用マニュアルの整備
トラブル時の対応方法やマニュアルを整備し、全社に周知して定着を図りましょう。
請求書電子化におすすめのツール【2025年版】
以下は、特に人気の高いクラウド請求書システムの一例です。
MakeLeaps(メイクリープス)
- 中小企業向けに設計された請求書管理ツール
- PDF送付、郵送代行、取引先管理も可能
- freeeやマネーフォワードとの連携もスムーズ
楽楽明細
- 大量の帳票処理に向いており、請求書以外の納品書・見積書も電子化可能
- 導入実績も多く、安心感あり
マネーフォワードクラウド請求書
- 会計や経費精算との一元管理が可能
- 自動で帳簿に反映されるため、経理業務の負担を大幅に軽減
freee請求書
- スタートアップや小規模法人に人気
- シンプルな操作性で、請求書・納品書の作成が簡単
BtoBプラットフォーム 請求書
- 上場企業や大企業とのやりとりが多い会社向け
- 取引先も多く利用しているため、導入のハードルが低い
電子化を成功させるための注意点と失敗例
- 社内ルールや役割分担が曖昧なまま進めてしまう
「誰が確認・送付・保管を担当するのか」を明確にしないと、確認漏れや二重処理が発生する恐れがあります。
- 取引先の電子化対応を確認していない
電子化しても、取引先が紙を求めている場合には混乱が起きることも。段階的な移行が必要です。
- 法的要件を満たしていない
電子帳簿保存法に対応するには、「真実性・可視性・検索性」を満たす必要があります。システム選定時に必ず確認しましょう。
まとめ|まずはできる範囲から、請求書の電子化を始めよう
請求書の電子化は、コスト削減・業務効率化・法令対応のすべてに効果がある、非常に価値の高い取り組みです。
- 小さく始めて、成功体験を積みながら拡大していく
- 社内ルールとツールを整えて、継続しやすい体制づくりを
- 取引先や法対応も見据えて、無理のない導入を
無料トライアル受付中|電子請求書の最適な保管方法
「何から始めればいいか分からない…」という方へ
▶️ [インボイス制度と電子帳簿保存法に対応した5Storage]