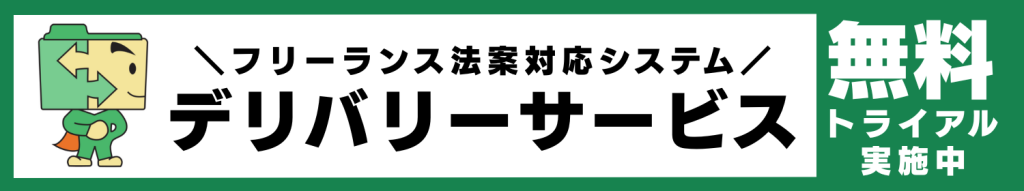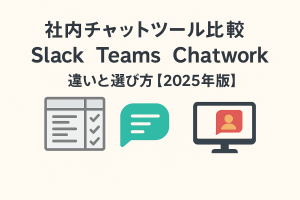2024年11月1日、政府はフリーランスの働き方を守るための新たな法律、「フリーランス保護法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」を施行しました。
この法律は、企業と個人の力関係に差が出やすいフリーランス契約の現場で、トラブルを防ぎ、安心して働ける環境を整備することを目的としています。
本記事では、フリーランス保護法の内容や影響を、わかりやすく5つのポイントに分けて解説します。
1. フリーランス保護法とは?簡単に言うとこういう法律です
フリーランス保護法は、企業などの発注者とフリーランス(=特定受託事業者)の取引に関して、適正な契約と報酬支払い、ハラスメント防止を義務付ける法律です。
なぜ今、フリーランスの法整備が必要なのか?
近年、会社に属さず個人で仕事を請け負う「フリーランス」の働き方が増えていますが、その一方で「口約束で契約が進む」「報酬が支払われない」「不当な値下げを強いられる」といったトラブルも後を絶ちません。
こうした背景から、国が一定のルールを設ける必要が出てきました。
この法律ができた背景と目的
厚生労働省や内閣官房が主導し、働き方改革の一環として制度化されました。目的は以下の2点に集約されます:
- 取引の透明化と契約の書面化
- ハラスメントや報酬未払いなど、立場の弱いフリーランスを守る
2. フリーランス保護法で何が変わるの?
この法律により、発注者とフリーランスの間で新たに守るべきルールが定められます。
契約書の書面化が義務に
業務の内容や報酬、納期、支払い条件などについて、書面または電子メールなどの文書での明示が義務付けられます。これにより、口約束で契約内容が曖昧なまま進むケースが減ります。
報酬の支払い遅延に対するルール整備
報酬は、納品後60日以内に支払うことが原則とされます。未払い・遅延の場合には、行政指導や勧告の対象となります。
ハラスメント対策の明文化
フリーランスに対するパワハラ・セクハラ行為についても、企業と同様に防止措置が義務づけられます。相談窓口の設置なども推奨されます。
3. 対象になるフリーランスとは?誰が関係あるの?
「私の働き方も対象になるの?」と不安な方もいるかもしれません。ここで対象範囲を明確にしておきましょう。
保護される働き方の定義
本法で保護されるのは、個人事業主として、反復・継続的に特定の業務を請け負っている人です。プログラマー、ライター、デザイナー、カメラマン、講師など、幅広い職種が該当します。
業務委託契約との関係
法人を設立している場合や、法人同士の契約は対象外です。ただし、「個人対企業」の業務委託契約が主な対象となるため、現在フリーランスとして活動している多くの人がこの法律の範囲に入ると考えて良いでしょう。
4. フリーランス保護法のメリットと課題
この法律ができることで、何が良くなり、何が課題となるのでしょうか。
フリーランス側のメリット
- 口約束ではなく契約内容が明文化される
- 報酬の支払いが確実に、かつ早くなる
- ハラスメントに対する相談体制が整う
安心して仕事を受けやすくなり、交渉力の弱いフリーランスにとっては大きな進歩です。
発注者(企業)側の注意点
- 契約書の整備が必須になる
- 支払い期日・ハラスメント防止の体制づくりが求められる
これまで「柔軟だった」やり取りが、やや形式的になる可能性もあります。
残る課題と今後の論点
- フリーランスの定義が曖昧なままなケース
- 法律を知らない発注者による違反行為の懸念
- トラブル発生時の対応窓口が機能するかどうか
制度の運用状況によっては、今後さらなる見直しもあり得ます。
5. 契約書・業務フローの見直しポイント
- 契約書ひな形を整備しておく
- 納期・報酬・成果物の範囲を明記する習慣をつける
- メールやチャットも保存して証拠化しておくと安心
トラブルを防ぐために意識すべきこと
- 契約のやりとりを記録に残す
- 法律の内容を把握し、自分の立場を理解する
- トラブル時には労働局や弁護士など専門機関に相談する
まとめ
フリーランス保護法は、これからの時代に必要不可欠な「安心して働くための基盤」となる法律です。
フリーランスという自由な働き方を守るために、自らも契約や権利についての知識を持っておくことが重要です。